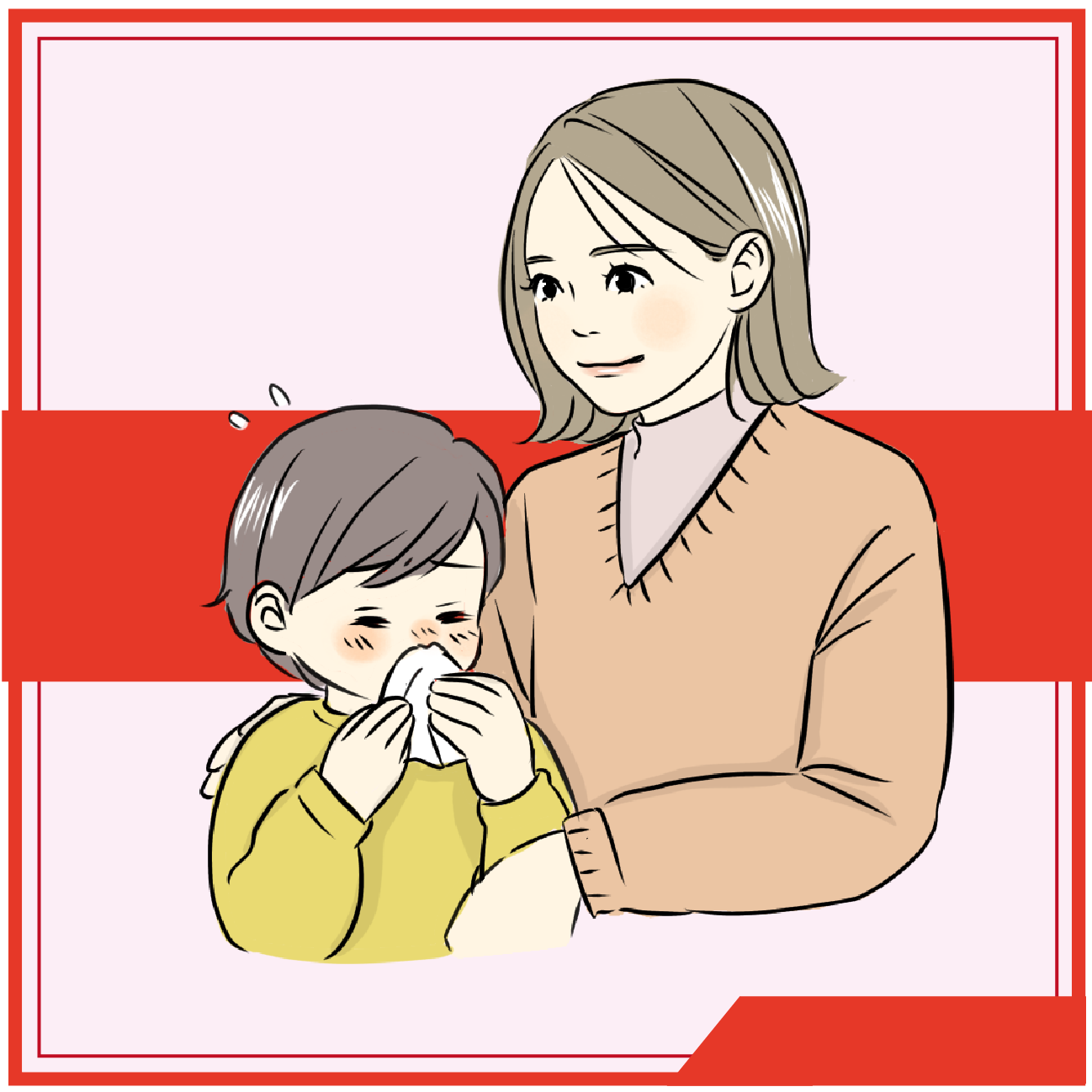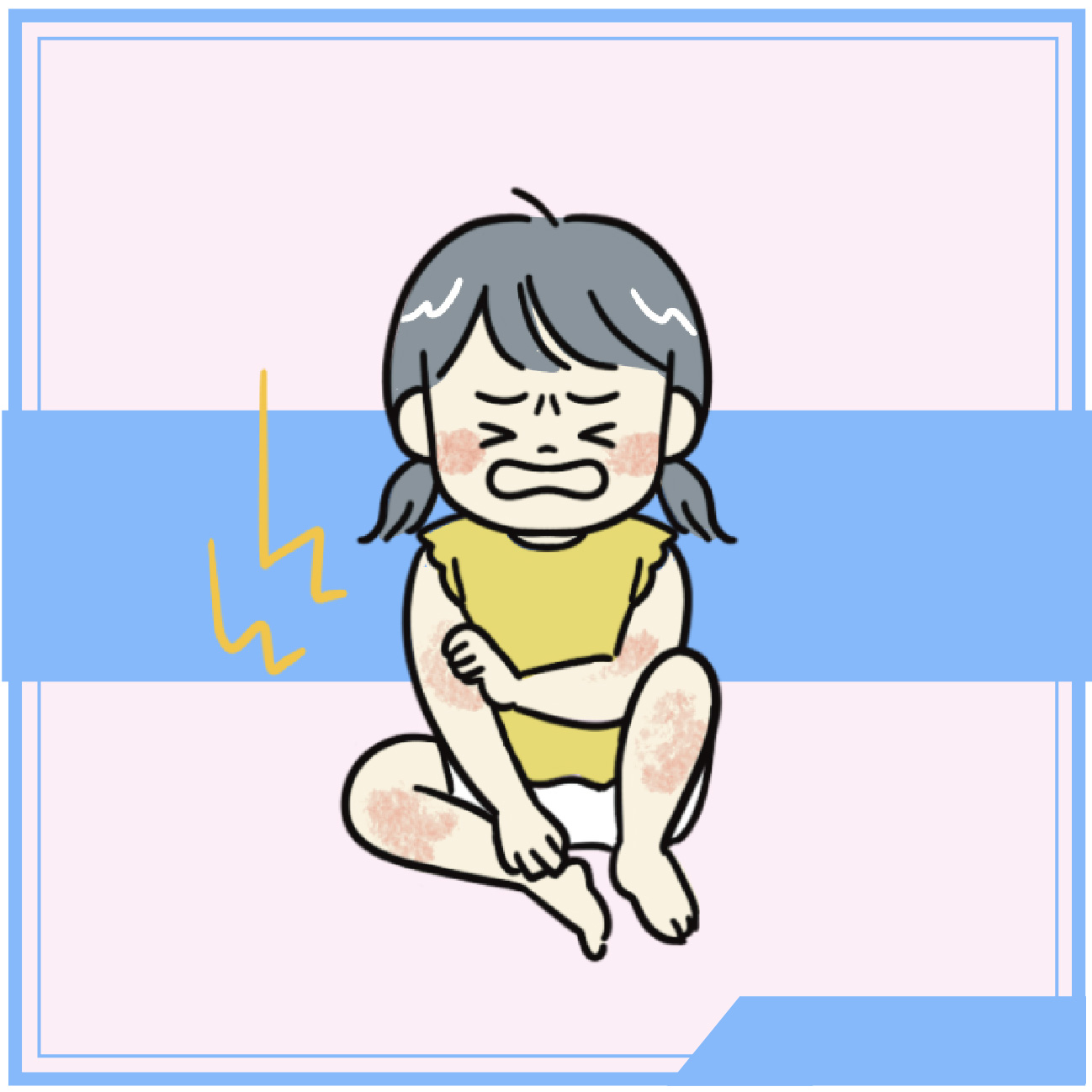妊娠中や産後、ママは赤ちゃんの健康が気になると思いますが、その中でもアレルギーを気にする方も多いのではないでしょうか。「ママのアレルギー体質は遺伝するの?」「アレルギー体質になりにくくするには?」この記事ではそのような疑問にお答えします。
確かに、遺伝的な要素でいうと、親がアレルギー体質である場合、赤ちゃんが同様のアレルギーを発症するリスクが高まる可能性があります。しかし、これはあくまでリスクの一要素であり、必ずしもアレルギー体質になるということではありません。
遺伝要因以外にアレルギーの発症に与える影響として、環境要因があげられます。赤ちゃんの生後期の食事、感染症の経験、生活環境などが、免疫システムの発達に影響を与え、アレルギーのリスクを増減させることがあるようです。
アレルギーの発症は、遺伝的要因と環境要因の相互作用によって引き起こされると考えられています。
つまり、「アレルギーになりやすい体質」が遺伝する可能性はありますが、ママがアレルギー体質だからといって、必ずしも赤ちゃんもアレルギーになるというわけではなく、生後期の環境要因なども関係してくるのですね。

・バランスの取れた食事
妊娠中や授乳期中、「アレルギーが心配な食材を避ける」ということに気を配るママも多いようです。しかし、過剰な食事制限は赤ちゃんの免疫システムの発達に影響を与える可能性があり、その結果、アレルギーのリスクが増加することがあります。そのため、特定の食材を避けるのでなく、さまざまな栄養素をバランスよく摂りましょう。魚類(サーモンや青魚)、乳製品(牛乳やヨーグルト)、豆類(豆腐や納豆)、葉野菜(ほうれん草やケール)、果物(オレンジやイチゴ)などはおすすめです。
・腸内環境を整える
腸の健康も重要です。腸は自律神経と密接な関係があり、腸内のバランスが整うことで免疫バランスも整えられます。妊娠中や授乳期中に腸内環境を整えて健康体でいると、赤ちゃんがアレルギー体質になりにくくなることに繋がります。具体的には、ヨーグルトや発酵食品、サプリメント、食物繊維などで善玉菌を増やし、腸内環境を整えることができます。
・十分な睡眠
睡眠不足や睡眠の質の低下はストレスホルモンの分泌を増加させ、免疫システムのバランスを崩してしまいます。これにより、アレルギー反応が過剰に活性化され、アレルギー症状が悪化する可能性があります。規則正しい睡眠サイクルを確保し、寝室を快適な睡眠環境にすることを心がけましょう。就寝前に入浴、ヨガ、ストレッチなど、リラックスすることも有効です。また、就寝前にスマホの画面を見るのは避けましょう。もし睡眠障害や不眠症が続く場合は、医師に相談することをおすすめします。



1.ママのアレルギー体質は子どもに遺伝するの?
妊娠中や授乳期中は特に、ママの健康が赤ちゃんに影響を与えます。アレルギーに悩むママは、自分の体質が遺伝するのではないかと不安に思うことがあるでしょう。確かに、遺伝的な要素でいうと、親がアレルギー体質である場合、赤ちゃんが同様のアレルギーを発症するリスクが高まる可能性があります。しかし、これはあくまでリスクの一要素であり、必ずしもアレルギー体質になるということではありません。
遺伝要因以外にアレルギーの発症に与える影響として、環境要因があげられます。赤ちゃんの生後期の食事、感染症の経験、生活環境などが、免疫システムの発達に影響を与え、アレルギーのリスクを増減させることがあるようです。
アレルギーの発症は、遺伝的要因と環境要因の相互作用によって引き起こされると考えられています。
「アレルギー疾患の遺伝子解析」京都大学大学院医学研究科健康要因学講座健康増進・行動学分野 鈴木雅雄 白川太郎(2005)
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/54/12/54_KJ00003984428/_pdf)
つまり、「アレルギーになりやすい体質」が遺伝する可能性はありますが、ママがアレルギー体質だからといって、必ずしも赤ちゃんもアレルギーになるというわけではなく、生後期の環境要因なども関係してくるのですね。

2.赤ちゃんがアレルギー体質になりにくくなるには?
では、アレルギー体質になりにくくなるために、具体的に妊娠中や授乳期中のママができることは何があるのでしょうか?・バランスの取れた食事
妊娠中や授乳期中、「アレルギーが心配な食材を避ける」ということに気を配るママも多いようです。しかし、過剰な食事制限は赤ちゃんの免疫システムの発達に影響を与える可能性があり、その結果、アレルギーのリスクが増加することがあります。そのため、特定の食材を避けるのでなく、さまざまな栄養素をバランスよく摂りましょう。魚類(サーモンや青魚)、乳製品(牛乳やヨーグルト)、豆類(豆腐や納豆)、葉野菜(ほうれん草やケール)、果物(オレンジやイチゴ)などはおすすめです。
・腸内環境を整える
腸の健康も重要です。腸は自律神経と密接な関係があり、腸内のバランスが整うことで免疫バランスも整えられます。妊娠中や授乳期中に腸内環境を整えて健康体でいると、赤ちゃんがアレルギー体質になりにくくなることに繋がります。具体的には、ヨーグルトや発酵食品、サプリメント、食物繊維などで善玉菌を増やし、腸内環境を整えることができます。
・十分な睡眠
睡眠不足や睡眠の質の低下はストレスホルモンの分泌を増加させ、免疫システムのバランスを崩してしまいます。これにより、アレルギー反応が過剰に活性化され、アレルギー症状が悪化する可能性があります。規則正しい睡眠サイクルを確保し、寝室を快適な睡眠環境にすることを心がけましょう。就寝前に入浴、ヨガ、ストレッチなど、リラックスすることも有効です。また、就寝前にスマホの画面を見るのは避けましょう。もし睡眠障害や不眠症が続く場合は、医師に相談することをおすすめします。

3.赤ちゃんのアレルギー発症を防ぐために
「アレルギーになりやすい体質」は遺伝する可能性があるものの、ママがバランスの取れた食事をしたり、腸内環境を整えたりして健康体でいることで、赤ちゃんのアレルギー予防に繋がります。妊娠中や授乳期から意識し、赤ちゃんと共に健康な身体をつくりましょう。まとめ
赤ちゃんがアレルギー体質になりづらくなるために、ママが妊娠中や授乳期中からできることをまとめました。例えご自身がアレルギー体質でも、必ずしも遺伝するというわけではないので、少しずつ無理なく実践していきましょう。

監修:星野 優 医師
医療法人社団 結樹会 理事長、スターフィールドクリニック横浜 院長
下大学病院勤務時代から消化管(特に大腸)を専門とし、様々な年齢層、疾患への豊富な診療経験を有する。現在も内視鏡検査及び各胃腸疾患に対して専門的な診療に従事。また、産業医として「働く世代」への医療的支援に注力している。
医療法人社団 結樹会 理事長、スターフィールドクリニック横浜 院長
下大学病院勤務時代から消化管(特に大腸)を専門とし、様々な年齢層、疾患への豊富な診療経験を有する。現在も内視鏡検査及び各胃腸疾患に対して専門的な診療に従事。また、産業医として「働く世代」への医療的支援に注力している。

監修:新藤 貴雄医師
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医、日本抗加齢医学会抗加齢専門医
足の静脈瘤クリニック横浜院院長
下肢静脈瘤の症状の回復に貢献するだけでなく、婦人科・不妊クリニックでの経験や知識も併せ持っている。
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医、日本抗加齢医学会抗加齢専門医
足の静脈瘤クリニック横浜院院長
下肢静脈瘤の症状の回復に貢献するだけでなく、婦人科・不妊クリニックでの経験や知識も併せ持っている。